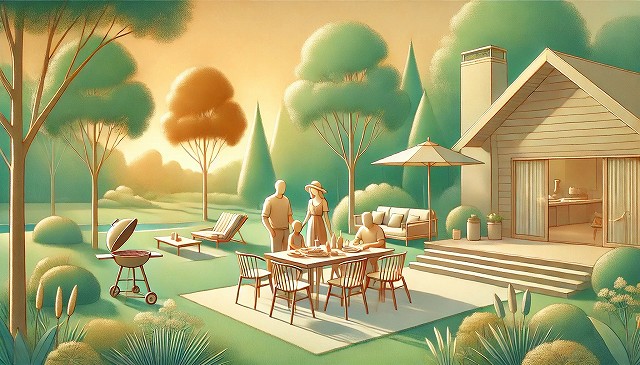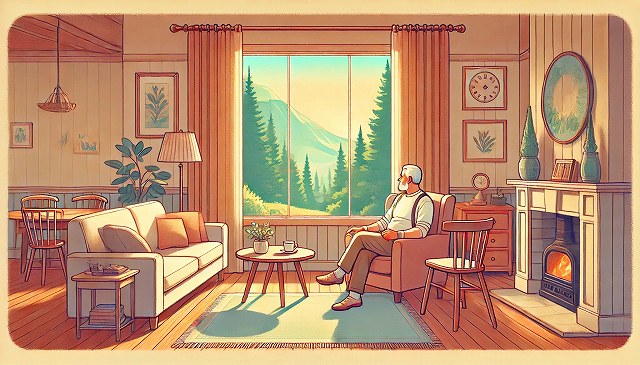退職後のセカンドライフを楽しむために「別荘購入」を検討するシニア世代が増えています。自然豊かな環境で過ごす時間や趣味を満喫するための拠点として魅力的な選択肢ですが、購入には注意点もあります。本記事では、別荘購入のメリットとデメリットを詳しく解説します。
別荘購入のメリット
別荘を持つことで得られる主なメリットをご紹介します。
1. 自然豊かな環境でリラックスできる
都市部の喧騒から離れ、緑豊かな環境や海辺で過ごすことで心身ともにリフレッシュできます。趣味やアウトドアを楽しむ拠点にも最適です。
2. 自由な時間を楽しめる
ホテルや旅館と異なり、自分のペースで自由に過ごせるのが別荘の魅力です。自分好みのインテリアや庭を整えることで、さらに快適な空間を作り出せます。
3. 家族や友人との交流の場になる
家族や友人を招いて一緒に過ごす場所としても活用できます。リタイア後の生活が充実し、交流が深まります。
4. 資産としての価値
立地や状態によっては資産価値が保たれる場合があります。また、貸し出すことで副収入を得ることも可能です。(別荘地の規約によっては、営利目的の貸し出しを禁止している場合があります。)
別荘購入のデメリット
一方で、別荘購入には注意すべき点も多くあります。
1. 維持費がかかる
別荘は購入費用だけでなく、以下のような維持費用が発生します:
- 固定資産税:別荘地の評価額に応じて毎年課税されます。
- 管理費:別荘地の共用部分の維持や清掃にかかる費用。
- 修繕費:老朽化した箇所の修繕や家屋のメンテナンス費用。
これらの費用は年間で数十万円以上になる場合もあり、継続的な出費が必要です。
なお、借地権の場合は固定資産税がかからないかわりに、年間地代を支払うかたちになります。
共益施設維持管理費は別荘地によって異なります。蓼科の某別荘地では75,240円/年、中軽井沢の別荘地では212,520円/年。
※管理費は土地面積に比例して高くなるのが一般的です。
その他費用として、私設水道を利用していることが多いため、年払いの水道基本料金が高めに設定されていたり、別荘購入時に共益施設補改修修繕積立金や水道施設補改修修繕積立金が必要になる場合もあります。
2. 利用頻度が限られる
せっかく別荘を購入しても思っていたほどは利用せず、という話もよく聞きます。使わない期間が長いと「宝の持ち腐れ」になってしまいますね。
自宅からの移動交通費が高くつくような立地だと、ある程度の長期滞在を計画しない限り別荘を持つメリットは薄れます。
年に1回しか利用しない別荘の場合、その1回の多くの時間を清掃に費やさなければならないこともあるので要注意です。
3. 近所づきあいの負担
別荘地でも近所づきあいが発生することがあります。ほとんどの別荘地は自治会的な組織がなく、地域とのつながりも薄いことが多いですが、まれに自治会があったり清掃活動への参加が求められるような場所もあります。
ご近所と付かず離れずの付き合い程度で過ごせる住環境なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
4. 交通アクセスの問題
都市部から離れた場所にあることが多いため、アクセスが不便な場合があります。高齢になると車の運転が難しくなり、移動手段が課題になることも。
自家用車での利用を前提で購入した場合、バス等の公共交通機関を利用しようと思ったらバス停や駅まで何キロも歩かなければならなかった、というような話は別荘地ではよくあることです。
ローカルの交通サービスがあっても、別荘地はサポートエリア外であることが多いようです。
別荘購入を検討する際のポイント
別荘購入を後悔しないためには、以下の点を考慮することが重要です:
購入前の現地確認
別荘地の雰囲気や近隣の環境を実際に訪れて確認しましょう。写真やインターネットだけではわからない情報が得られます。
特に開発されてから何十年も経っている別荘地では、樹木が成長しすぎて日照が遮られ、物件の周りが薄暗くなっていることがあります。
維持費を見積もる
購入費用だけでなく、年間でかかる維持費を事前に計算しておきましょう。固定資産税や管理費が高額にならないか確認が必要です。
リセールバリューを意識する
将来的に売却する可能性を考え、立地や周辺環境が良い物件を選ぶことが大切です。人里離れた自然の中がいいといっても、最寄りのスーパーまで1時間かかるようでは利用しているうちに不便を感じるようになります。
利用目的を明確にする
「週末の休暇用」や「定住目的」など、具体的な目的を明確にすることで選択が絞りやすくなります。夏季だけの利用であれば設備や家屋構造にそれほどこだわる必要はないかもしれませんが、冬季も利用する予定があるのならば、高気密・高断熱の家を建てるとか薪ストーブを導入する等の配慮が必要になります。
また、家庭菜園をしたくて購入する人は、管理規約で菜園が禁止されていないか注意する必要があります。
最低限の生活インフラが整うかを確認する
生活する際にインフラ面で問題があると困ります。上下水道や電気、ごみ出し等に不便はないか、あらかじめ確認する必要があります。
また、日常の買い物をするのに不便がないかということも重要です。”一番近いスーパーまで車で30分”という環境は、便利な生活に慣れている人にとっては苦痛になりかねません。
別荘購入が向いている人とは?
以下のような人には別荘購入がおすすめです:
- 自然豊かな環境で趣味を楽しみたい:ガーデニングや釣り、ハイキングを満喫したい方。
- 定期的に訪れる計画がある:月に1回以上別荘を利用する予定がある方。
- 資産に余裕がある:維持費や管理費を負担できる経済力がある方。
- 家族や友人と過ごす拠点が欲しい:交流の場を重視する方。
どんな場所でも家は建てられる?
「山奥に安い土地を購入したので別荘を建てよう」と考えたときは、次のような点を考慮しておく必要があります。
上水道が引けない場合:
公営の上水道が利用できないような土地の場合は井戸を掘る必要があります。
井戸掘りの初期費用
掘削費用: 井戸の深さによって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
浅井戸(20〜40m): 約20万〜50万円程度
深井戸(50m以上): 約60万〜100万円程度。
ポンプ設置費用: 井戸から水を汲み上げるためのポンプの費用は、種類によって異なります。
ジェットポンプ(浅井戸用): 数万円〜20万円程度
水中ポンプ(深井戸用): 20万円〜数十万円程度。
配管工事費用: 井戸から家まで水を引くための配管工事も必要です。これには追加の費用がかかります。
その他の初期費用
水質検査費用: 井戸水の安全性を確認するための水質検査が必要です。これには1万〜数万円程度かかることがあります。
維持費
井戸を掘った後には、以下のような維持費が発生します。
ポンプのメンテナンス: ポンプの交換や修理が必要になることがあります。これには年間数万円の費用がかかることが一般的です。
水質検査: 年に1回の水質検査を行うことが推奨されており、これも維持費に含まれます。
ポンプの運転にかかる電気代: ポンプの種類や使用頻度によりますが、月々の電気代が数千円から数万円かかることがあります
下水道が引けない場合
下水道が引けない土地に家を建てる場合、下水処理施設として浄化槽を設置する必要があります。
浄化槽の設置費用
浄化槽の設置には、本体および設置工事その他で一般的に80万円から140万円程度の初期費用がかかります。具体的な費用は、浄化槽の種類や規模(人槽数)によって異なります。
浄化槽本体の価格: 5人槽の場合、約80万円程度が相場です。7人槽や10人槽になると、さらに高額になります。
工事費用: 浄化槽の設置工事にかかる費用も含まれます。これには、土木工事や配管工事が含まれます。
浄化槽の維持費
浄化槽を設置した後には、以下のような維持費が発生します。
保守点検費用: 年間約2万円から3万円程度。浄化槽の機能を維持するために、定期的な点検が必要です。
清掃費用: 年に1回の清掃が必要で、これには約2万6,000円から5万円程度かかります。
法定検査費用: 年に1回の法定検査が必要で、これには約5,000円程度の費用がかかります。
電気代: 浄化槽の運転に必要な電気代も年間で数千円から1万円程度かかることがあります。
年間維持費の合計は一般的に約5万円から9万円程度が目安です。
電気が引けない場合
電気が引けない山奥に家を建てる場合は、自家発電システムの導入や蓄電池の利用、エネルギー効率の高い設計(小さな家にする 等)が重要です。
地域の法律や規制を確認し、必要なライフラインを確保することも忘れずに行いましょう。
ごみ集積場が利用できない場合
自治会の管理下にないような場所の場合、ごみ収集所は利用できません。自分でごみ処理場に持ち込む必要があります。この場合、処理場でのごみ処理は有料で、重量に応じた料金が発生することがあります。
重機が入っていけない場合
重機が入れない場所では、通常の建築方法ではなく、手作業や小型の機材を使った施工が必要になります。これにより、工事のコストが高くなる可能性があります。
まとめ
別荘は、シニア世代にとって憧れのライフスタイルを実現するための魅力的な選択肢ですが、維持費や利用頻度、近隣とのつながりなど、事前に考慮すべき点も多くあります。
購入を検討する際は、自分の生活スタイルや経済状況に合った選択をすることが大切です。しっかり準備をして、理想のセカンドライフを楽しみましょう!